防衛省職員によるセクハラ事件で話題となった国家賠償法の判決。 「なぜ加害者個人ではなく国が賠償するのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。
この判決は、公務員の職務上の行為について定めた国家賠償法という重要な法律に基づいています。
一般的には理解しにくい制度ですが、被害者保護と公務の適正な運営という両面を考慮した仕組みなのです。
そこでここでは国家賠償法の仕組みと公務員の個人責任について詳しく解説していきます。
実際に国家賠償法が適用された事例についてもまとめてみましたのでご覧ください。
【防衛相職員によるセクハラ訴訟からみる国家賠償法】
・判決内容と市民の反応
・国家賠償法の基本的な仕組み
・公務員個人の責任が否定される理由
・過去の具体的事例
・制度の課題と今後の展望
防衛省セクハラ事件の訴訟の概要と判決内容
では防衛省職員のセクハラ事件の訴訟の概要と判決内容について詳しく紹介いたします。
2025年7月11日、東京地裁で注目すべき判決が下されました。
防衛省の男性職員から継続的なセクハラを受けたとして、同僚の女性職員が国と男性職員に計600万円の損害賠償を求めた訴訟です。
こちら一覧にまとめてみましたのでご覧ください。
【事件の概要】
・発生期間:2020年4月から約1年間
・加害者:防衛省の男性職員
・被害者:同じ部署の女性職員
・請求額:国と男性職員に計600万円の損害賠償
【セクハラ行為の内容】
・勤務中に女性の二の腕や下半身をもむ行為
・休日の外出時に抱きつく行為
・継続的かつ悪質な性的嫌がらせ
【判決内容】
・セクハラ行為があったと認定
・国に250万円の支払いを命令
・一場康宏裁判長「性的自由に対する侵害の程度は強い」と厳しく指摘
・被害女性は2022年に適応障害を発症
・休日の行為も職務に付随すると判断
特に注目すべきは、休日の行為についても「職務に付随した行為」と判断された点です。
判決では、女性が職場での関係悪化を恐れて断れなかった状況を重視し、勤務時間外であっても職場の上下関係が影響していたと認定しました。
この判断により、男性個人への請求は棄却され、国家賠償法に基づき国のみが賠償責任を負うことになったのです。
女性は事件後の2022年に適応障害を発症しており、継続的な被害の深刻さが浮き彫りになっています。
この訴訟に対する市民の反応について
それでは、この判決に対する市民の反応を詳しく見ていきましょう。
Yahoo!ニュースのコメント欄には250件を超える意見が寄せられ、多くの市民が強い関心を示しています。
最も多い反応は「加害者個人に賠償責任を負わせるべき」という意見でした。
ある市民は「ハラスメント被害により加害者が特定されている場合は国や行政が支払う賠償金を加害者に100%請求すべきである。 賠償金を税金で補填されることがあってはならない」
とコメントしています。
一方で、国家賠償法の専門知識を持つ方からは「きちんと加害者にも請求が行く法律ですよ」という制度の説明も見られました。
しかし、実際には求償権の行使は限定的で、多くの場合に加害者個人への請求は行われていないのが現状です。
このような市民の声からは、国家賠償制度に対する理解不足と、税金での賠償に対する不満が浮き彫りになっています。
そこで次に、多くの方が気になる公務員の個人責任について見ていきましょう。
公務員には賠償責任がないの?
このように多くの人が疑問に思っている公務員の賠償責任について。
「なぜ加害者個人ではなく国が責任を負うのか」という声が数多く寄せられています。
そこでここからは国家賠償法の基本的な仕組みについて解説することで、この制度の理解を深めていきたいと思います。
国家賠償法の基本的な仕組み
国家賠償法は、公務員の職務上の違法行為について特別な責任制度を定めています。
第1条では以下のように規定されています。
【国家賠償法1条1項】
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責めに任ずる
【国家賠償法1条2項】
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する
この制度の基本的な考え方は、まず国が被害者に対して賠償を行い、その後必要に応じて加害公務員に求償するという二段階の仕組みです。
最高裁が公務員の個人責任を否定する理由
最高裁は一貫して、公務員個人は被害者に対して直接の賠償責任を負わないと判示しています。
この判断の背景には、以下のような実質的な根拠があります。
【被害者救済の確実性】
・公務員個人の資力では十分な賠償ができない可能性がある
・国が責任を負うことで確実な被害者救済を図る
・被害者が泣き寝入りすることを防ぐ制度設計
【公務の萎縮防止】
・公務員が個人責任を恐れて適切な公務執行を躊躇することを防ぐ
このように、公務員個人の資力では十分な賠償ができない可能性があるため、国が責任を負うことで確実な被害者救済を図っています。
また、公務員が個人責任を恐れて適切な公務執行を躊躇することを防ぐため、一定の保護が必要とされています。
警察官による逮捕、検察官による起訴、税務職員による滞納処分など、権力行使を伴う公務では特に重要な配慮となっております。
求償権制度の実情と課題
国家賠償法第1条第2項は、公務員に故意又は重大な過失がある場合の求償権を規定しています。
しかし、現実的には求償権の行使は極めて限定的です。
求償権は「有する」という表現で、義務ではなく権利として規定されているため、国の裁量に委ねられています。
実際に求償が行われるケースは稀で、多くの場合は懲戒処分にとどまっているのが現状です。
この点について、国民からはより積極的な求償権行使を求める声が上がっています。
今回のセクハラ訴訟からみる国家賠償法について解説
このような理解のもとで、今回の防衛省セクハラ事件の判決を検証してみましょう。
職務関連性の判断基準
今回の判決で争点となったのは、セクハラ行為が「職務に関連する行為」と言えるかどうかでした。
勤務中の行為については明らかに職務関連性が認められますが、休日の外出時の行為についても職務に付随するものと判断されました。
裁判所は、職場での上下関係や同僚関係が休日の行為にも影響していたと認定しています。 女性が職場での関係悪化を恐れて断れなかった状況を重視した判断です。
セクハラ事案における国家賠償の適用範囲
公務員のセクハラ事案では、職務関連性の判断が重要なポイントになります。
過去の裁判例を見ると、以下のような傾向があります。
・職員に広く参加を呼びかけた懇親会でのセクハラ発言
→国家賠償責任を認定
・私的な懇親会後のホテルラウンジでのセクハラ
→国家賠償責任を否定、個人責任を認定
今回の事案は前者のパターンに該当し、職場の同僚関係に基づく継続的な行為として国家賠償責任が認められました。
被害者保護と制度の課題
国家賠償制度は被害者保護を第一の目的としていますが、同時に様々な課題も抱えています。
税金による賠償に対する国民の理解と、加害者への適切な責任追及のバランスが重要な課題となっています。
今回の事案では、防衛省が「ハラスメントを一切許容しない環境を構築していく」とコメントしており、組織的な再発防止策の強化が期待されています。
過去にあった国家賠償法の事例
それでは、国家賠償法が適用された過去の重要な事例について詳しく紹介していきます。
森友学園文書改ざん事件における個人責任の扱い
近年最も注目された事例の一つが、森友学園に関する財務省の決裁文書改ざん事件です。
元近畿財務局職員の赤木氏が自殺したことを受け、ご遺族が国と当時の理財局長佐川氏に損害賠償を求めました。
大阪地裁は2022年11月25日、佐川氏個人に対する請求を棄却しました。
最高裁判例に従い、公務員個人は賠償責任を負わないという理由です。 国に対する請求については、国が認諾(請求を全て認めて裁判を終了)したため、真相解明には至りませんでした。
自衛官による性暴力事案と個人責任
元自衛官の女性が在職中の性的被害を告発した事案では、加害者側弁護士が「個人責任を問われるか疑問がある」として示談交渉を行いました。
この発言に対してインターネット上では批判が相次ぎましたが、法的には正当な主張でした。
被害女性は2023年1月に国と加害者個人の両方に対して損害賠償請求訴訟を提起しています。
「自衛隊の公務とは関係がなく、違法性が非常に高い」として個人責任を追及していますが、判決の行方が注目されています。
新宮市議会での名誉毀損事案
地方議会でも国家賠償法が適用される事例があります。
新宮市では、元市議の女性が現職市議の男性に名誉を傷つけられたとして、市に慰謝料200万円の支払いを求めて提訴しました。
特別職の市議も公務員に含まれ、議場内での発言が職務にあたるため、市が被告となりました。
市は弁護士費用約69万円を計上し、応訴することになっています。
この事例は、個人間の対立が税金を使った訴訟に発展することへの市民の疑問も呼んでいます。
国家賠償事例から見える制度の特徴
これらの事例から、国家賠償制度の以下のような特徴が見えてきます。
・公務員の職務関連行為に適用
・違法性の程度に関わらず国が責任を負う
・被害者は確実な救済を受けられる
・加害者個人への直接的な責任追及は困難
・求償権の行使は限定的
・実際の個人への責任転嫁は稀
これらの特徴は、制度の目的である被害者保護を達成する一方で、加害者への制裁効果や抑止効果については課題を残しています。
公務員の賠償責任と国家賠償についてまとめ
ここまで公務員の賠償責任である国家賠償法について紹介してきました。
国家賠償制度は、公務員の職務上の違法行為について国が責任を負う仕組みです。
この制度により被害者は確実な救済を受けられる一方で、加害者個人の責任追及については限界があることも明らかになりました。
こちら一覧にまとめてみましたのでご覧ください。
・根拠法:国家賠償法(昭和22年制定)
・適用対象:国又は公共団体の公務員の職務上の行為
・責任主体:国又は公共団体(個人ではない)
・求償権:故意又は重大な過失がある場合に限定
・判例:最高裁は一貫して公務員個人の責任を否定
・目的:被害者救済の確実性と公務の適正な執行の両立
・課題:税金による賠償への国民理解と加害者責任のバランス
今回の防衛省セクハラ事件の判決は、この制度の基本的な考え方を改めて示したものです。
被害者保護を最優先としつつ、組織的な再発防止策の強化と求償権のより積極的な活用が今後の課題となるでしょう。
国家賠償制度について理解を深めることで、公務員の責任と国民の権利についてより適切な議論ができるようになります。
制度の趣旨を理解した上で、より良い仕組みへの改善を求めていくことが重要です。

今後も公務員の適切な責任追及と被害者保護の両立に向けた議論が続くことを期待しています。
ここまで読んでいただきましてありがとうございます。


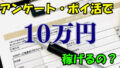
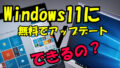
コメント